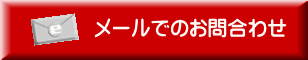���{��s�̍s�����m����@���������́A�Õ������̐\���葱������Ƃ���n�斧���^�̍s�����m�������ł��B
�d�b�ł̂��₢���킹��TEL.072-361-4220
��587-0052 ���{��s�������]��20-11
�@�@�@�z�[���@>�@�Õ������̎擾���@�i�P���c�Ɓj
�Õ������̎擾���@�i�P���c�Ɓj
�P�D���i���R�ɊY�����Ȃ����Ƃ̊m�F
�Õ��c�Ɩ@�ł́A���L�̂悤�Ȍ��i���R�ɊY������Ƌ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƋL�ڂ���Ă��܂��B��������`�F�b�N���܂��傤�B
�����āA�Õ����́A�Ǘ��҂Ɏ�舵���Õ����s���i�ł��邩�ǂ����f���邽�߂ɕK�v�Ȃ��̂Ƃ��Ĉ��̒m���A�Z�p���͌o��������悤�w�߂Ȃ���Ȃ�܂���B�Ƃ��Ɏ����ԁA������֎Ԗ��͌����@�t���]�Ԃ���舵���c�Ə����͌Õ��s��̊Ǘ��҂ɂ��Ă̈��̒m���A�Z�p���͌o���Ƃ́A�s���i�̋^�������鎩���ԁA������֎Ԗ��͌����@�t���]�Ԃ̎ԑ́A�ԑ�ԍ��ō��������ɂ�����������̗L�����тɉ�����������ꍇ�ɂ͂��̑ԗl�y�ђ��x�肷�邽�߂ɕK�v�Ƃ����m���A�Z�p���͌o���̂��Ƃ������܂��B����́A���̒m���A�Z�p���͌o����K�v�Ƃ���Õ��c�Ƃ̋Ɩ��ɎO�N�ȏ�]�������҂��ʏ�L���Ă���A���@ �i�����Q�X�N�@����W�X���j��R�S�� �̋K��ɂ��ݗ����ꂽ�@�l���̑��̒c�̂��s���u�K�̎�u���̑��̕��@�ɂ�蓾�邱�Ƃ��ł���B
����ɊǗ��҂����̐E���Ɋւ��@�߂̋K��Ɉᔽ�����ꍇ�A�����ψ���͊Ǘ��҂Ƃ��ĕs�K���ł���ƔF�߂��Ƃ��́A�Õ����ɑ��A���̊Ǘ��҂̉�C���������邱�Ƃ��ł��܂��B
�y�Ǘ��҂̌��i���R�z
�y�l���Ƃ̏ꍇ�z
�������A���ۂɂ͒��ړs���{�������ψ���ɐ\���������o����̂ł͂Ȃ��A�c�Ə��i�c�Ə��̂Ȃ��҂ɂ����ẮA�Z�����͋����j�̏����x�@�������o�R���āA�����Q�ʂ̋��\�������o���܂��B
�܂��A����s���{�����łQ�ȏ�̉c�Ə����c�Ƃ���ꍇ�́A���ꂼ��̉c�Ə��̂��������ꂩ�P�̉c�Ə��̏��ݒn�̏����x�@�������o�R���āA�����Q�ʂ̋��\�������o���܂��B�v����ɁA����s���{�����łQ�ȏ�̉c�Ə����c�Ƃ���ꍇ�́A1�ӏ��̏����x�@�������o�R���āA1�ӏ��̌����ψ���ɒ�o���A�����邱�ƂɂȂ�܂��B���R�A�Q���ɂ܂�����Q���̂��ꂼ��̌����ψ���ɋ��\�������o���ċ����Ȃ���Ȃ�܂���B
�܂��A���\�������\���̒�o��Ƃ���Ă���@�ւ̎������ɓ��B���Ă��炻�̐\���ɑ��鋖������܂ł̊��ԁi�W���������ԁj�́A�S�O�����炢�i�e�s���{���ɂ���Ă��ƂȂ�j�ƂȂ��Ă��܂��B
- ���N��㌩�l�������͔�ۍ��l�܂��͔j�Y�҂ŕ����Ȃ�����
�@ - �����ȏ�̌Y�ɏ������A���͑�R�P���ɋK�肷��߂������͌Y�@
�i�����S�O�N�@����S�T���j��Q�S�V��
�A��Q�T�S���������͑�Q�T�U���Q���ɋK�肷��߂�Ƃ��Ĕ����̌Y�ɏ������A���̎��s���I���A���͎��s���邱�Ƃ̂Ȃ��Ȃ�������N�Z���ĂT�N���o�߂��Ȃ���
�@�i�Y�@�F�@��247���i�w�C�j �A��254���i�⎸�������́j�A��256���2���i���i�̉^���A�ۊǁA�L������A�L���̏���
�@�@�̂�������j�j
�@ - �Z���̒�܂�Ȃ���
�@ - ��Q�S���̋K��ɂ�肻�̌Õ��c�Ƃ̋�����������A���Y������̓�����N�Z���ĂT�N���o�߂��Ȃ��ҁi�����������ꂽ�҂��@�l�ł���ꍇ�ɂ����ẮA���Y������ɌW�钮���̊����y�яꏊ���������ꂽ���O�U�O���ȓ��ɓ��Y�@�l�̖����ł����҂œ��Y������̓�����N�Z���ĂT�N���o�߂��Ȃ����̂��܂ށB�j
�@ - ��Q�S���̋K��ɂ�鋖�̎�����ɌW�钮���̊����y�яꏊ���������ꂽ�����瓖�Y���������������͓��Y����������Ȃ����Ƃ����肷����܂ł̊Ԃɑ�W���P����P���̋K��ɂ�鋖�̕Ԕ[�������ҁi���̌Õ��c�Ƃ̔p�~�ɂ��đ����ȗ��R������҂������B�j�ŁA���Y�Ԕ[�̓�����N�Z���ĂT�N���o�߂��Ȃ�����
�@ - �c�ƂɊւ����N�҂Ɠ���̔\�͂�L���Ȃ������N�ҁB�������A���̎҂��Õ������͌Õ��s���̑����l�ł��āA���̖@��㗝�l���O�e���̂�����ɂ��Y�����Ȃ��ꍇ���������̂Ƃ���B
�@ - �c�Ə����͌Õ��s�ꂲ�Ƃɑ�P�R���P���̊Ǘ��҂�I�C����ƔF�߂��Ȃ����Ƃɂ��đ����ȗ��R�������
�@ - �@�l�ŁA���̖����̂����ɑ�P�������T���܂ł̂����ꂩ�ɊY������҂��������
�Q�D�Ǘ��҂̌���
�Ǘ��҂Ƃ́A�c�Ə��ɌW��Ɩ���K���Ɏ��{���邽�߂��ӔC���̂��Ƃł���A�c�Ə����ƂɊǗ��҈�l��I�C���Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��A���L�̌��i���R�ɊY������҂͊Ǘ��҂ɂ͂Ȃ邱�Ƃ��ł��܂���B�����āA�Õ����́A�Ǘ��҂Ɏ�舵���Õ����s���i�ł��邩�ǂ����f���邽�߂ɕK�v�Ȃ��̂Ƃ��Ĉ��̒m���A�Z�p���͌o��������悤�w�߂Ȃ���Ȃ�܂���B�Ƃ��Ɏ����ԁA������֎Ԗ��͌����@�t���]�Ԃ���舵���c�Ə����͌Õ��s��̊Ǘ��҂ɂ��Ă̈��̒m���A�Z�p���͌o���Ƃ́A�s���i�̋^�������鎩���ԁA������֎Ԗ��͌����@�t���]�Ԃ̎ԑ́A�ԑ�ԍ��ō��������ɂ�����������̗L�����тɉ�����������ꍇ�ɂ͂��̑ԗl�y�ђ��x�肷�邽�߂ɕK�v�Ƃ����m���A�Z�p���͌o���̂��Ƃ������܂��B����́A���̒m���A�Z�p���͌o����K�v�Ƃ���Õ��c�Ƃ̋Ɩ��ɎO�N�ȏ�]�������҂��ʏ�L���Ă���A���@ �i�����Q�X�N�@����W�X���j��R�S�� �̋K��ɂ��ݗ����ꂽ�@�l���̑��̒c�̂��s���u�K�̎�u���̑��̕��@�ɂ�蓾�邱�Ƃ��ł���B
����ɊǗ��҂����̐E���Ɋւ��@�߂̋K��Ɉᔽ�����ꍇ�A�����ψ���͊Ǘ��҂Ƃ��ĕs�K���ł���ƔF�߂��Ƃ��́A�Õ����ɑ��A���̊Ǘ��҂̉�C���������邱�Ƃ��ł��܂��B
�y�Ǘ��҂̌��i���R�z
- ���N��㌩�l�������͔�ۍ��l�܂��͔j�Y�҂ŕ����Ȃ�����
�@ - �����ȏ�̌Y�ɏ������A���͑�R�P���ɋK�肷��߂������͌Y�@
�i�����S�O�N�@����S�T���j��Q�S�V��
�A��Q�T�S���������͑�Q�T�U���Q���ɋK�肷��߂�Ƃ��Ĕ����̌Y�ɏ������A���̎��s���I���A���͎��s���邱�Ƃ̂Ȃ��Ȃ�������N�Z���ĂT�N���o�߂��Ȃ���
�@�i�Y�@�F��247���i�w�C�j �A��254���i�⎸�������́j�A��256���2���i���i�̉^���A�ۊǁA�L������A�L���̏����̂�������j�j
�@ - �Z���̒�܂�Ȃ���
�@ - ��Q�S���̋K��ɂ�肻�̌Õ��c�Ƃ̋�����������A���Y������̓�����N�Z���ĂT�N���o�߂��Ȃ��ҁi�����������ꂽ�҂��@�l�ł���ꍇ�ɂ����ẮA���Y������ɌW�钮���̊����y�яꏊ���������ꂽ���O�U�O���ȓ��ɓ��Y�@�l�̖����ł����҂œ��Y������̓�����N�Z���ĂT�N���o�߂��Ȃ����̂��܂ށB�j
�@ - ��Q�S���̋K��ɂ�鋖�̎�����ɌW�钮���̊����y�яꏊ���������ꂽ�����瓖�Y���������������͓��Y����������Ȃ����Ƃ����肷����܂ł̊Ԃɑ�W���P����P���̋K��ɂ�鋖�̕Ԕ[�������ҁi���̌Õ��c�Ƃ̔p�~�ɂ��đ����ȗ��R������҂������B�j�ŁA���Y�Ԕ[�̓�����N�Z���ĂT�N���o�߂��Ȃ�����
�@ - �����N��
�R�D���\�����ނ̍쐬
�Õ������̐\��������ɂ́A���L�̏��ނ��K�v�ł��B�쐬�y�їp�ӂ����܂��傤�B�y�l���Ƃ̏ꍇ�z
- ���\����
�@ - �ŋ߂T�N�Ԃ̗������L�ڂ�������
�@ - �Z���[�̎ʂ��i�O���l�ɂ����Ă͊O���l�o�^�ؖ����̎ʂ��j
�@ - ���i���R�ɊY�����Ȃ��|���L�ڂ�������
�@ - ���N��㌩�l���͔�ۍ��l�ɊY�����Ȃ��|�̓o�L�����ؖ���
�@ - ���N��㌩�l�Ƃ݂Ȃ����ҁA��ۍ��l�Ƃ݂Ȃ����ҁA�]�O�̗�ɂ�邱�ƂƂ���鏀�֎��Y�Җ��͔j�Y�҂ŕ����Ȃ����̂ɊY�����Ȃ��|�̎s�����i���ʋ�܂ށB�j�̒��̏ؖ�
�@ - �I�C����Ǘ��҂̍ŋ߂T�N�Ԃ̗������L�ڂ�������
�@ - �I�C����Ǘ��҂̏Z���[�̎ʂ��i�O���l�ɂ����Ă͊O���l�o�^�ؖ����̎ʂ��j
�@ - �I�C����Ǘ��҂����i���R�ɊY�����Ȃ��|���L�ڂ�������
�@ - �E�����N�ҁi�����ɂ�萬�N�ɒB�������̂Ƃ݂Ȃ����҂������B�j�ŌÕ��c�Ƃ��c�ނ��ƂɊւ��@��㗝�l�̋����Ă����
�@�@�@�@�@��㗝�l�̎����y�яZ�����L�ڂ�������
�@�@�@�A�@��㗝�l�̋����Ă��邱�Ƃ����鏑��
�E�Õ������͌Õ��s���̑����l�ł��関���N�҂ŌÕ��c�Ƃ��c�ނ��ƂɊւ��@��㗝�l�̋����Ă��Ȃ���
�@�@�@�@�푊���l�̎����y�яZ�����L�ڂ�������
�@�@�@�A�Õ��c�ƂɌW��c�Ə����͌Õ��s��̏��ݒn���L�ڂ�������
�@�@�@�B�@��㗝�l�̍ŋ߂T�N�Ԃ̗������L�ڂ�������
�@�@�@�C�@��㗝�l�̏Z���[�̎ʂ��i�O���l�ɂ����Ă͊O���l�o�^�ؖ����̎ʂ��j
�@�@�@�D�@��㗝�l�̌��i���R�i��L�@�P�D�`�T�D�j�ɊY�����Ȃ��|���L�ڂ�������
�@ - �z�[���y�[�W���g�p���ĉc�Ƃ�����ꍇ�́A���̃z�[���y�[�W�̂t�q�k���g�p���錠���̂��邱�Ƃ�a�����鎑��
�@�@
- ���\����
�@ - �芼
�@ - �o�L�����ؖ���
�@ - �����̍ŋ߂T�N�Ԃ̗������L�ڂ�������
�@ - �����̏Z���[�̎ʂ��i�O���l�ɂ����Ă͊O���l�o�^�ؖ����̎ʂ��j
�@ - �����̐��N��㌩�l���͔�ۍ��l�ɊY�����Ȃ��|�̓o�L�����ؖ���
�@ - �����̐��N��㌩�l�Ƃ݂Ȃ����ҁA��ۍ��l�Ƃ݂Ȃ����ҁA�]�O�̗�ɂ�邱�ƂƂ���鏀�֎��Y�Җ��͔j�Y�҂ŕ����Ȃ����̂ɊY�����Ȃ��|�̎s�����i���ʋ�܂ށB�j�̒��̏ؖ�
�@ - �����̌��i���R�i��L�@�P�D�`�T�D�j�ɊY�����Ȃ��|���L�ڂ�������
�@ - �I�C����Ǘ��҂̍ŋ߂T�N�Ԃ̗������L�ڂ�������
�@ - �I�C����Ǘ��҂̏Z���[�̎ʂ��i�O���l�ɂ����Ă͊O���l�o�^�ؖ����̎ʂ��j
�@ - �I�C����Ǘ��҂����i���R�ɊY�����Ȃ��|���L�ڂ�������
�@ - �z�[���y�[�W���g�p���ĉc�Ƃ�����ꍇ�́A���̃z�[���y�[�W�̂t�q�k���g�p���錠���̂��邱�Ƃ�a�����鎑��
�S�D���\�����ނ̒�o
�Õ������\�����ނ̍쐬�y�їp�ӂ��ł��܂�����A�c�Ə��i�c�Ə��̂Ȃ��҂ɂ��ẮA�Z�����͋����j�����݂���s���{�������ψ���ɐ\�����܂��B�������A���ۂɂ͒��ړs���{�������ψ���ɐ\���������o����̂ł͂Ȃ��A�c�Ə��i�c�Ə��̂Ȃ��҂ɂ����ẮA�Z�����͋����j�̏����x�@�������o�R���āA�����Q�ʂ̋��\�������o���܂��B
�܂��A����s���{�����łQ�ȏ�̉c�Ə����c�Ƃ���ꍇ�́A���ꂼ��̉c�Ə��̂��������ꂩ�P�̉c�Ə��̏��ݒn�̏����x�@�������o�R���āA�����Q�ʂ̋��\�������o���܂��B�v����ɁA����s���{�����łQ�ȏ�̉c�Ə����c�Ƃ���ꍇ�́A1�ӏ��̏����x�@�������o�R���āA1�ӏ��̌����ψ���ɒ�o���A�����邱�ƂɂȂ�܂��B���R�A�Q���ɂ܂�����Q���̂��ꂼ��̌����ψ���ɋ��\�������o���ċ����Ȃ���Ȃ�܂���B
�T�D�s�����̐R��
�Õ����̋��̊�Ƃ��ẮA���i���R�ɊY�����Ȃ��ȂnjÕ��c�Ɩ@�����炵�A�K���ȉc�Ƃ����҂ł���Ƃ��ɋ����邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A���\�������\���̒�o��Ƃ���Ă���@�ւ̎������ɓ��B���Ă��炻�̐\���ɑ��鋖������܂ł̊��ԁi�W���������ԁj�́A�S�O�����炢�i�e�s���{���ɂ���Ă��ƂȂ�j�ƂȂ��Ă��܂��B
�U�D���̌�t
���v�������Ă���A�����ψ�����������Ƃ��́A���̌�t���Ȃ���܂��B����ɂāA�Õ��c�Ƃ����邱�Ƃ��ł��܂��B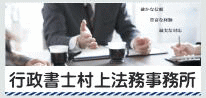

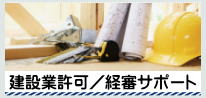

| �c�ƒn�� |
| �w���{�S��x �E��s���E��s����E��s���� �E��s���E��s�k��E��s���� �E��s������E���s������� �E���s�����E���s������� �E���s����E���s�s���� �E���s�k��E���s������ �E���s���ԋ�E���s�ߌ��� �E���s�铌��E���s������ �E���s����E���s�`�� �E���s������E���s�V������ �E���s�Q����E���s�吳�� �E���s�����E���s���{��� �E���s������E���s����� �E���s���Z�g��E���s�Z�g�� �E���s�Z�V�]��E�a��s�E���Ύs �E��㋷�R�s�E�x�c�юs �E�͓�����s�E���Îs�E�ݘa�c�s �E�L�ˎs�E��s�E���s�E���s �E�����s�E�H�g��s�E���䎛�s �E�����s�E�����s�E�����s �E�哌�s�E�l���s�E���s �E��^�s�E����s�E�Q����s �E�ےÎs�E�����s�E���Ύs�E���c�s �E�L���s�E�r�c�s�E���ʎs�E��؎s �E�\���S�E���S�E��k�S�E�O���S �E��͓��S �w���Ɍ��x �E�_�ˎs�S��E�����s�E���Ύs �E���s�E�ɒO�s�E�쐼�s�E�O�c�s �E���{�s�E��ˎs�E�O�؎s�E�����쒬 �w�ޗnj��x �E����s�E�����s�E���Ŏs�E����s �E�䏊�s�E�V���s�E�ޗǎs �E��a�S�R�s�E��a���c�s�E����S �E���S�E�k����S �w�a�̎R���x ���{�s�E�a�̎R�s �E���̑��̒n��͑��k�ɉ��������Ă��������܂��B |
| �����N�ɂ��� |
| ���T�C�g�ւ̃����N�͘A���s�v�ő劽�}�ł��B�܂��A���݃����N��]�̕��͎��O�ɂ��A�����������B�������A�@�߈ᔽ���̎Љ�ʔO��s�K�ȃT�C�g�Ƃ̃����N�͂��f�肢�����܂��B�����N��͌����Ƃ��āA���T�C�g�̃g�b�v�y�[�W�ɂȂ�܂��B �y�t�q�k�z http://www.kobutsukyoka.biz �y�T�C�g���z �Õ������\���葱���̂��ƂȂ���{��s�̍s�����m����@�������� �y�Љ�z ���{��s�̍s�����m����@���������́A�r�W�l�X�p�[�g�i�[�Ƃ��ĉ�Аݗ�����Õ������̋��\���A���̌�̉^�c�܂ł̋N�ƁE�^�c���T�|�[�g���Ă���܂��B |
shop info���{��s�̍s�����m�̎��������
�s�����m����@��������
��587-0052
���{��s�������]��20-11
TEL.072-361-4220
FAX.072-344-5873
E-mail�@achiachi7019@yahoo.co.jp
�c�Ǝ��ԁ@9:00�`18:00
��x���@ �@�y���j
�@�@�@�@����������x���ł���˗��ɉ����đΉ���
�@�@�@�@�@���Ă��������܂�